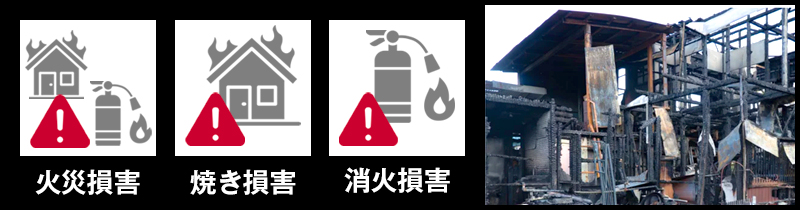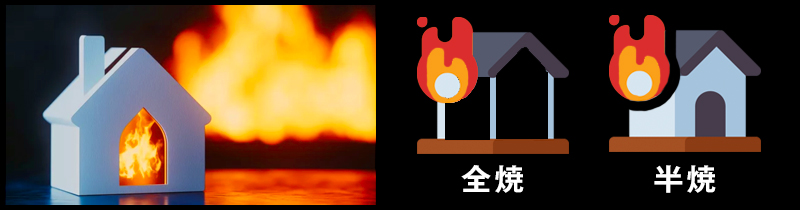火災によって建物が損傷した場合、被害の程度を判断するために「全焼」や「半焼」といった用語が使われます。これらの定義は、日常的なイメージだけでなく、消防や保険の現場において明確に定められた基準に基づいて判断されます。
当記事では、「火災損害」「焼き損害」「消火損害」といった用語の意味を整理しつつ、消防庁および保険会社それぞれの「全焼」「半焼」の定義を解説します。保険金の支払いに影響を及ぼす要素や、火災保険の補償が受けられないケースなども紹介します。
1.全焼の定義を理解する上で押さえたい用語
火災保険や損害調査の現場において「全焼」と認定されるには、明確な定義と評価基準があります。火災による損害を適切に把握するには、「火災損害」「焼き損害」「消火損害」といった用語の意味を正確に知ることが大切です。
1-1.火災損害
火災損害とは、火事によって直接的に生じた損害を指します。火災損害は「焼き損害」と「消火損害」を合わせたものであり、消火活動にかかった経費などの間接的損失は含まれません。
火災損害の大きさは、建物や収容物の損傷程度に基づいて「全損」「半損」「小損」に分類されます。たとえば、損害額が建物の評価額の70%以上に達すると「全損」となり、保険金の算定にも影響します。
1-2.焼き損害
焼き損害とは、火災の炎や高熱により直接焼失・破損・変色などの被害を受けた損害を指します。たとえば、火で焼けた住宅設備や家財、高温により変質・変色した壁や床などが該当します。
焼き損害は火災損害の中でも最も顕著に現れる部分であり、建物全体の焼失状況を把握する上で重要な評価指標となります。火災保険の請求や被害認定の際には、焼き損害の範囲と内容が詳細に確認されます。
1-3.消火損害
消火損害とは、火災を消し止めるための消火活動によって生じた損害です。主な例として、放水によって濡れてしまった壁や床、破損した天井、さらには水濡れによる漏電のリスクが挙げられます。見た目には火による焼損がない場合でも、放水の影響によって大きな損害が発生することも少なくありません。
消火損害も火災損害に含まれるため、保険金の算定や被害の認定時には焼き損害とあわせて評価されます。
2.全焼・半焼とは?
「全焼」や「半焼」といった言葉は、ニュースなどでも頻繁に使われる表現ですが、消防庁ではこれらに明確な定義を設けています。ここでは、全焼・半焼の定義を詳しく解説します。
2-1.全焼の定義
消防庁では、建物の焼損部分の損害額が火災前の評価額の70%以上に達したもの、または70%未満であっても補修後に再使用できない状態のものを「全焼」と定義しています。つまり、構造体が著しく損傷し、建て直しが必要とされるケースです。
総務省消防庁の『消防白書』によると、建物火災で亡くなった方のうち60%以上が全焼の火災によるものであり、生命へのリスクが非常に高い火災であることが分かります。構造物全体に火が及び、逃げ遅れや救助困難な状況に陥りやすいため、規模の大きさと危険性はきわめて深刻です。
2-2.半焼の定義
半焼とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の評価額の20%以上70%未満であり、全焼に該当しないものを指します。外見では一部が残っていても、内部の一部が激しく焼損していれば半焼と認定されるケースもあります。
死者が発生した火災のうち、約12%が「半焼」に該当しており、全焼に比べれば低いものの、重大な被害をもたらす火災であることに変わりはありません。特に、集合住宅では延焼や煙の充満によって避難に支障が出ることもあります。建物の構造や管理体制によっては、半焼でも大規模修繕や一部解体が必要となります。
3.保険会社による全焼と半焼の認定基準の違い
火災が発生した場合、火災保険を利用して原状回復を行うには、建物が全焼かどうかを保険会社が独自に判断する必要があります。ただし、保険会社の判断が一方的にならないよう、第三者である損害鑑定人が現地調査を行い、その結果に基づいて補償の可否や範囲が決定されます。
この基準は、消防署の判断とは異なる場合があり、建物の損傷評価や保険約款に即して判断されることを覚えておきましょう。
3-1.全焼と認定する基準
保険会社では、消防署とは異なり「消火損害」も含めて被害の大きさを判断します。そのため、消防署が「半焼」と判断した火災でも、消火時の放水被害や破損が甚大な場合には、保険会社が「全焼」として扱うケースがあります。
損害鑑定人による調査の結果、以下のいずれかの条件を満たすと「全焼」と認定されます。
- 延べ床面積の70%以上が焼損
- 原状回復費用が保険金額を上回る
- 火災損害額が保険金額の80%を超える
- 消防署による全焼判定がある
全焼と認定された場合、契約時に設定した保険金額の全額が支払われるため、原状回復に要する費用を広くカバーできます。
3-2.半焼と認定する基準
火災保険の約款上には「半焼」という明確な区分は存在しません。保険会社が「全焼」と認定しなかった場合、「部分的な焼損」として扱われるのが一般的で、これを半焼と呼ぶことがあります。
部分焼損と判断された場合、保険会社は「焼き損害」と「消火損害」の合計金額を査定し、それに応じた保険金が支払われます。ただし、火元が被保険者の重大な過失に起因する場合や、補償対象外のケースでは、半焼であっても保険金が支払われないこともあります。
また、地震を原因とする火災については、火災保険ではなく地震保険の補償範囲です。火災の原因によって適用される保険が異なる点にも注意が必要です。
4.全焼・半焼でも保険金を受け取れないケースは?
火災によって建物が全焼あるいは半焼したとしても、火災保険金が必ず支払われるとは限りません。特に「重大な過失」や「故意」「法令違反」などが原因で火災が発生した場合には、免責事項として保険金が支払われないケースがあります。
重大な過失とは、わずかな注意を払えば火災を防げたにもかかわらず、それを漫然と見過ごした状態を指します。たとえば、てんぷら油を加熱中にその場を長時間離れて出火した事例や、寝たばこの危険性を認識していながら喫煙を続けて火災に至った事例などは、過去の裁判でも重大な過失と認定されています。
また、火災の原因が地震や噴火、津波によるものであった場合、火災保険では補償対象外となり、別途地震保険に加入していないと保険金は支払われません。このほか、経年劣化や自然の消耗・ねずみや虫による損害、異常な事態(戦争・核事故など)による損害も免責となります。
5.地震で発生した火災は火災保険の補償対象外になる
地震を原因として発生した火災については、原則として火災保険の補償対象外となります。地震や噴火、津波による火災や損害は、火災保険ではなく地震保険でカバーされます。
地震保険は、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、定められた割合の保険金が支払われる仕組みです。地震の多い日本においては、資産を守るために火災保険とあわせて地震保険への加入を検討しましょう。
愛知県・名古屋で火災現場の片付け業者選びにお悩みならアイコムにお任せください!
火災による建物被害は、「全焼」や「半焼」などの定義に基づいて評価されます。消防庁では損害割合に応じて明確な区分を設けており、保険会社もこれに加え、保険金額や損害鑑定の結果に基づいて補償内容を判断します。
ただし、火災の原因によっては火災保険の対象外となるケースもあります。適切な補償を受けるためには、保険の契約内容や火災時の対応を日頃から確認しておきましょう。
また、火災が発生したときは火災現場の片付けも必要です。その後の対応でお困りの方は、ぜひアイコムにご相談ください。