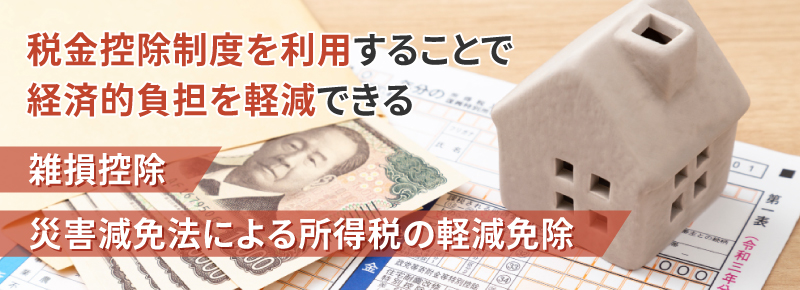火災によって住宅や家財が焼失した場合、多くの人が精神的にも経済的にも大きなダメージを受けます。突然の出費に備えがないまま被災してしまうと、生活の再建に困難を伴うことも少なくありません。
しかし、市区町村による災害見舞金や、罹災証明書を用いた廃棄物処理費用の減免、緊急の生活資金を支援する貸付制度など、火災による被災者を支援するための公的制度や補助金、税制優遇措置が各種用意されています。
当記事では、火事による経済的負担を軽減するために知っておきたい制度や費用の目安を解説します。
1.火事が起きたときの補助金や支援制度
火事が発生した際には、被災者の生活再建や片づけに対する公的な支援制度を活用することが重要です。自治体や社会福祉協議会では、状況に応じてさまざまな補助や貸付制度を設けています。以下では、代表的な支援制度について紹介します。
1-1.災害見舞金
災害見舞金とは、火災や風水害などで被害を受けた世帯・個人に対し、自治体が支給する見舞金のことです。生活再建の初期支援として役立つ制度ですが、金額や対象の条件などは自治体ごとに異なります。以下に、名古屋市と山形県の災害見舞金の内容を比較します。
| 被害区分 | 名古屋市 | 山形県(上限) | |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 2人以上世帯 | ||
| 住家の全壊(全焼・流失) | 7万円 | 9万円 | 30万円以内 |
| 住家の半壊(半焼) | 5万円 | 7万円 | 20万円以内 |
| 床上浸水 | 3万円 | 5万円 | 10万円以内 |
| 死者 | 10万円/1人 | – | |
災害見舞金の申請は名古屋市の場合は住んでいる地域の区役所に相談し、山形県では県から対象者に連絡が入る仕組みになっています。申請手順の流れについてもあらかじめ知っておくとよいでしょう。
1-2.一般廃棄物処理費用減免制度
一般廃棄物処理費用減免制度とは、火災や自然災害によって発生したごみを処理する際に、通常かかる処分手数料を自治体が減免する制度です。災害後は家具や家財道具の破損などで大量の廃棄物が発生することもあり、経済的負担の軽減を目的とした支援策として設けられています。ただし、対象範囲や減免割合、手続き方法は自治体によって異なります。
以下に、名古屋市と横浜市の制度内容を比較します。
| 項目 | 名古屋市 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 対象ごみ | 災害で発生した粗大ごみ・家庭系ごみなど | 火災・天災で発生した一般廃棄物 |
| 処理費用 | 収集または自己搬入いずれも減免対象 | 自己搬入分の手数料(13円/kg)を全額免除 |
| 利用条件 | 各区役所の環境事業所に相談 | 被害を受けた場所の行政区の資源循環局収集事業所へ事前の申請が必要(被災後90日以内) |
1-3.応急小口資金の貸付
「応急小口資金(緊急小口資金)」とは、急な失業や災害、病気などで一時的に生活が困難になった人に対して、生活の立て直しを支援するための貸付制度です。対象は主に低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯などで、無利子で最大10万円まで借りられるケースが一般的です。申請には一定の要件があるため、事前に内容を確認しておくことが大切です。
以下では、名古屋市と大阪市で実施されている緊急小口資金貸付制度の概要を比較します。
| 項目 | 名古屋市 | 大阪市 |
|---|---|---|
| 対象者 | 低所得・障害者・高齢者世帯 | 生活困窮世帯で自立支援を受けている者等 |
| 金額上限 | 最大10万円 | 最大10万円(審査により最小限に調整) |
| 利子 | 無利子 | 無利子(延滞時は年3%) |
| 償還期間 | 12か月以内(据置2か月以内) | 12か月以内(据置2か月以内) |
| 償還方法 | 月賦(口座引落しまたは払込票による返済) | 一括または月賦(口座振替) |
| その他 | 区社会福祉協議会で申請 | 必要書類に加え、自立支援機関の意見書が必要 |
2.火事が起きたときに使える税金控除制度
火災による被害を受けたときには、被災者の経済的負担を軽減するための税金控除制度を利用できる場合があります。一定の条件を満たすことで、所得税の軽減や免除を受けられる制度が設けられています。ここでは「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」という2つの制度について解説します。
2-1.雑損控除
雑損控除は、火災や風水害、盗難などによって生活に必要な資産に損害を受けた際に、所得税の負担を軽くする制度です。納税者本人や生計をともにする一定の親族が所有する、生活に通常必要な資産が対象となります。控除額は以下のいずれか多い方です。
(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
引用:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」/ 引用日2025/06/18
災害関連支出には、焼けた住宅の撤去費用などが含まれます。保険金を受け取った場合は、損害額から差し引いて計算します。また、対象者や対象物は以下の通りです。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
引用:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」/ 引用日2025/06/18
なお、所得1,000万円以下の人は「災害減免法による所得税の軽減免除」の選択も可能で、状況に応じて有利な方を選べます。
2-2.災害減免法による所得税の軽減免除
災害減免法による所得税の軽減免除とは、災害により大きな損害を受けた納税者に対し、その年の所得税を軽減または免除する制度です。雑損控除と同様に火災による損失が対象となりますが、両制度は併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。
この制度の適用を受けるには、住宅や家財の損害額がその時価の2分の1以上、かつその年の所得金額が1,000万円以下であることが条件です。所得金額に応じて、下表のように所得税が全額または一部免除されます。
| 所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 所得税の額の全額 |
| 500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
引用:国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」/ 引用日2025/06/18
対象となる住宅や家財は、納税者本人または生計を一にする配偶者・親族(所得48万円以下)が所有し、生活に通常必要とされるものに限られます。
申請には、被害の状況と損害額を記載した確定申告書等を税務署に提出する必要があります。確定申告の期限後でも申請可能で、修正申告や更正の請求でも選択可能です。
3.火事で燃えた建物の解体費用相場
火事で被害を受けた建物の解体費用は、構造や面積、被害の程度によって大きく異なります。一般的な相場は1坪あたり2万円~6.5万円程度とされており、構造別・面積別の費用相場は以下の通りです。
■構造別 坪単価の目安
| 構造 | 坪単価の目安 |
|---|---|
| 木造 | 約2万円~4.5万円 |
| 鉄骨造 | 約4万円~5.5万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 約4.5万円~6.5万円 |
■坪数別 総費用の目安
| 坪数 | 解体費用の目安 |
|---|---|
| 30坪 | 約60万円~180万円 |
| 50坪 | 約150万円~300万円 |
| 100坪 | 約300万円~600万円 |
火災により損傷した建物は、煤や有害物質の除去、特別な機材の使用が必要になる場合もあり、通常の解体よりも費用が高くなる傾向にあります。立地や家屋の状態によっても費用は変動するため、複数の解体業者に見積もりを依頼することが重要です。
4.火災が起きた後解体の前にするべき手続き
火災が発生した直後は混乱しがちですが、解体工事に取りかかる前に行うべき手続きが複数あります。必要な処理を順に進めることで、保険金や税金控除などの支援を受けやすくなり、復旧も円滑になります。以下に、解体前に行っておくべき主な手続きを時系列でまとめました。
| 手続き内容 | 詳細 |
|---|---|
| 被害現場の撮影 | 現場の状況を記録することで、保険金請求や税金控除の申請時に証拠資料として活用できます。できるだけ火災の痕跡が分かる状態で複数角度から撮影しましょう。 |
| 罹災証明書の発行 | 火災にあったことを公的に証明する書類です。市区町村の消防署で申請可能で、保険請求や各種支援制度の利用時に必須となります。 |
| 貴重品の回収 | 立ち入りが可能であれば、現場から重要な書類や通帳、印鑑などを速やかに回収してください。火災後は盗難や再出火のリスクもあるため、早急な対応が重要です。 |
| 保険会社への連絡 | 火災保険に加入している場合、罹災証明書を取得した後に速やかに連絡を入れましょう。現地調査が終わる前に解体すると保険金が支払われない可能性があるため、解体前に連絡が必須です。 |
| 税金の減免申請 | 被害状況によっては、雑損控除や災害減免法などの制度を活用して所得税の減額が可能です。対象となるかは税務署で相談する必要があります。 |
手続きが完了後、解体工事の事前調査・届出・近隣説明などへと進みます。被害が大きいほど補助や保険の恩恵も大きくなるため、証明書や記録の取得は確実に行いましょう。
愛知県・名古屋で火災現場の片づけの業者選びにお悩みならアイコムにお任せください!
火災発生時には、災害見舞金・廃棄物処理費用減免・応急小口資金貸付などの公的支援制度が利用できます。税制面では雑損控除や災害減免法による所得税軽減も可能です。解体前には被害現場の撮影、罹災証明書取得、保険会社への連絡、税金減免申請などの手続きを順序立てて行うことで、各種支援を効果的に活用できます。
火災現場の片付けや現状回復にお困りの方は、全国対応の専門会社「アイコム」にぜひご依頼ください。戸建てやマンション、工場火災まで幅広く対応しており、火災後の不安やお悩みも丁寧にサポートしています。